「パチンコホール 法律ハンドブック」監修者が解説
警察行政のパチンコホール営業への規制の方向性とその変遷
文 = 三堀 清(弁護士)/text by Mihori Kiyoshi
今回は、風適法による規制の変遷を説明する。
この点については、まずは、2006年4月に公表された鶴代隆造警察庁生活安全課課長補佐(当時)の「ぱちんこ営業の健全化を推進する取組状況について~平成16年7月1日以降の状況~」(「警察学論集」第59巻第4号84頁~)に注目したい。
鶴代論文では、ホール営業には、射幸性を訴求した営業方法の弊害、営業に関する違法行為の問題、不明朗なグレーゾーンの存在、という三つの健全性阻害要因があり、規制及び健全化の推進の主眼は、これらの要因の除去にあるとするのである。
射幸性を訴求した営業方法の弊害とは、パチンコは1995年のピーク以降、売上高及び参加人の減少が続く中、ホール業者は少数のヘビーユーザーの争奪に走り、遊技機の射幸性が高まり、結果的に投資金額の多額化とのめり込みの問題が顕在化したということである。
そして、この問題への対策として、警察庁は、2004年7月に内閣府令、施行規則及び遊技機規則を各改正し、パチスロの射幸性をかなり抑制していた。
また、ホール関係者に向け、2011年6月に「ぱちんこ営業における広告、宣伝等について(通知)」を、2012年7月に「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の徹底について(通知)」を各発し、禁止される著しく射幸心をそそるおそれのある広告・宣伝の表現を例示した。
2017年9月には施行規則及び遊技機規則を改正し、ギャンブル等依存症対策として遊技機の出玉性能をさらに抑制した。
次に営業に関する違法行為の問題とは、遊技機の射幸性を高める不正改造が増加したということである。
この対策として、警察庁は、先の2004年の規則改正でパチスロの射幸性抑制と共に遊技機の性能の基準として不正改造が困難な構造とすることを盛り込んだ。
して、2006年8月の有限責任中間法人(現・一般社団法人)遊技産業健全化推進機構の設立も共通の文脈にある。
不明朗なグレーゾーンの存在とは、くぎ及び換金の問題である。適法な行為の如く、「整備」や「調整」と称して出玉性能変更のためのくぎ曲げをしたり、ホール業者が無関係な第三者を装って賞品の買取りをした実態があるが、前者は遊技機の無承認変更、後者は賞品の自家(直)買いであり、違法行為である。
くぎ曲げについては、警察庁は、2015年4月に遊技産業健全化推進機構にくぎチェックのために遊技機性能調査を要請し、ホール5団体に向けて同年5月に「遊技機の不正改造の絶無に向けたさらなる取組みについて(要請)」を、同年11月には「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機の撤去について(要請)」を発し、くぎ曲げの根絶とくぎ曲げを稼働の前提とする遊技機の自主撤去を要請した。
換金については、警察庁は、換金需要の低減化のため、いずれもホール5団体に向け、2006年2月に「賞品の取りそろえの充実について」を発し、カタログ景品や貯玉再プレイシステムを推奨したが、2011年10月に「ぱちんこ営業における適切な賞品提供の徹底について(通知)」を、2013年10月に「ぱちんこ営業に係る賞品の更なる推進について(通知)」を立て続けに発している。換金需要の低減化の前提となる賞品の取り揃えが進まなかったためであり、2015年4月にはモデル処分基準を改正し、現金等提供禁止違反・賞品買取禁止違反の量定をB(40日以上6月以下の営業停止。基準期間3月)に引き上げている。

■ 三堀 清
丸ビル綜合法律事務所パートナー(元・三堀法律事務所代表)、弁護士。元・PCSA法律分野アドバイザー。パチンコホールをはじめ企業関連の民事事件を手掛ける。風営適正化法及び廃棄物処理法関連業種の事案、閉鎖会社の内紛および債権回収、滞納管理費等の回収から派生したマンション管理に関する事案などを得意分野とする。

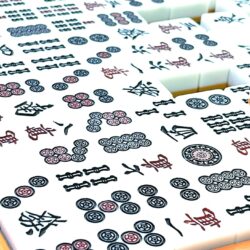




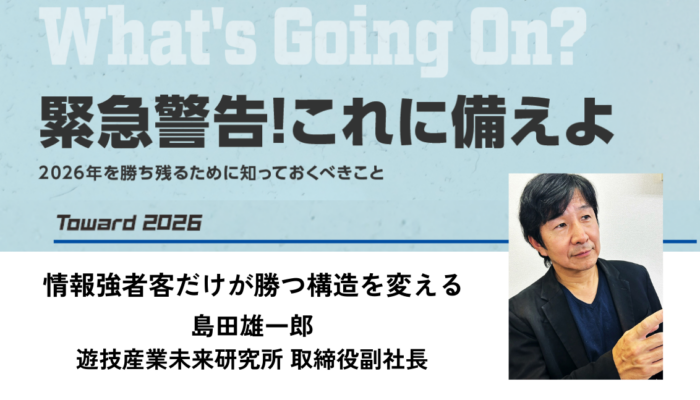










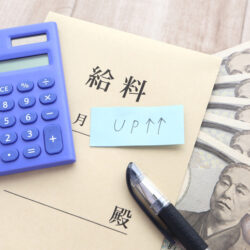

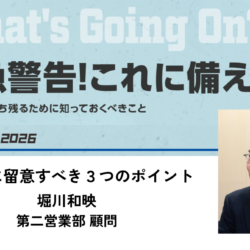
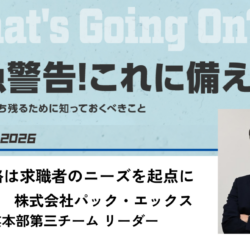
コメント